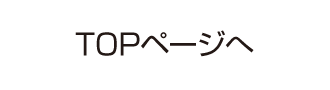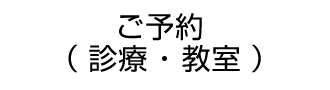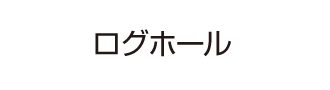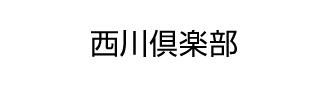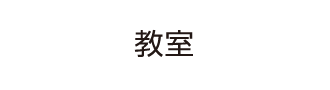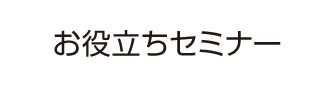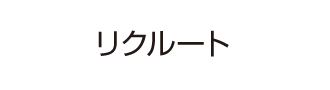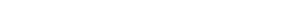無痛分娩をお考えの方へ
無痛分娩(硬膜外麻酔分娩)に対する思い
私達の大切な役目
分娩には痛みと苦しみがつきものですが、痛みや苦しみがなければ、母性が芽生えず、母親になれないのでしょうか?
いえ、決してそんなことはありません。西川医院では、元気な赤ちゃんを産んでいただくだけでなく、お母さま方の痛みや苦しみを和らげることも私たちの大切な役目と考えています。
痛みや苦しみを減らす方法
そこで、私たちは1997年から硬膜外麻酔を用いる分娩(無痛分娩)を行ってきました。さらに近年は、母性の熟成に重きを置くソフロロジー分娩法(薬物によらない鎮痛法)と、無痛分娩(薬物よる鎮痛法)を柔軟に組み合わせ、スムーズな分娩となるようにサポートしています。
麻酔の特徴を伝えよう
完全に痛みも感覚もなくすには、濃い局所麻酔薬をたくさん使う必要があります。実は、そのような麻酔は不適切であり、経膣分娩に必要な子宮の収縮を止めてしまいます。さらに、下半身にうまく力が入らず、いきめなくなります。分娩時間が長引いたり、帝王切開へ切り替えねばならなくなるのです。
ですから、経膣分娩に使う麻酔は、薄い局所麻酔薬で、最小限の量にとどめ、痛みだけに作用させます。感覚は残り、分娩の進行に伴ってお腹やお尻には強い圧迫感が現れます。その頃には足を動かして分娩の体勢をとり、圧迫感に合わせてしっかりと腹圧をかけ、いきむことができるのです。
おかげさまで、当院では多くの方が痛みゼロでご出産されています。ただし、強い圧迫感だけでなく、状況によっては、途中で痛みを感じる時間帯があるかもしれません。
ほかにも、安全を優先するがゆえの特徴が色々ありますので、当院の教室で理解を深めてからご利用いただくことをおすすめします。
当院の無痛分娩(硬膜外麻酔分娩)の解説
準備していただきたいこと
痛みがあるからといって麻酔を早く始めるわけではありません。開始時期が早すぎると、子宮収縮が弱まり、分娩時間が長引いてお身体に負担がかかってしまいます。
スムーズな分娩のために大切なのは、陣痛で子宮口が開きやすく、赤ちゃんが産道を通りやすいような身体作りです。当院では妊娠中からおすすめの有酸素運動やヨガ、ソフロロジー呼吸法、栄養指導、メンタルケアの教室を提供しています。一緒に準備していきましょう。
無痛分娩(硬膜外麻酔分娩)の開始時期
分娩当日は、ソフロロジー呼吸法を併用しながら、スタッフが個々に適切な麻酔開始時期を見極めています。
- 子宮口が4cmに開大
- 子宮頸管の熟化
- 児頭の下降
- 十分な子宮収縮
これらの条件が全て満たされている時が、最適と考えています。
大切にしていること
お産は十人十色ですから、お母さまの思いや分娩経過の安全性を大切にしています。
- ※入院のタイミング
腹痛、腰痛、出血、破水など、いつもと違う症状が現れてきたら、お食事を止めた状態で、お早めに病院へご連絡ください。
※陣痛間隔が10分以内になるのを待たないでください
無痛分娩(硬膜外麻酔分娩)を行う場合は、子宮口が4cm程度に開大して、自然の子宮収縮が少なくとも20分以内に1回あるころから入院するのが理想的です。初期陣痛自覚の時期は、夜中が多いので、我慢せずに早朝に入院しておきましょう。 - ※計画無痛分娩
前期破水や予定日超過など、医学的に分娩を進める必要がある場合に限り、行なっています。
他にも、前回の分娩時間が短かった等の理由で計画無痛分娩をご希望の場合は、ご相談ください。子宮口の状態によっては安全な陣痛の誘発が困難なこともあります。その際は、計画が叶わない場合もあることをご了承ください。 - ※途中からの無痛分娩切り替え
ご希望に沿って24時間対応可能です。ただし、少しでも切り替えの可能性がある場合は、当院が提供している麻酔について、教室で事前学習していただくようお願いします。十分なご理解のもとで切り替えていただくことをおすすめします。
ご予約の流れ
麻酔開始決定後の大まかな流れ
- 絶食(嘔吐や誤嚥の予防)
- 点滴(低血圧の予防)
- 硬膜外カテーテル留置
- モニタリング
- 血圧をこまめに測定
- 分娩監視《子宮内圧測定と胎児心拍数モニタリング》
- 麻酔の導入
・低濃度の局所麻酔薬を使用
※母児の安全のために緩やかに調整します。お産が急激に進行すると、痛みがゼロになるまでに時間を要することがあります。速効性のある脊髄くも膜下麻酔は、赤ちゃんの心拍数を低下させるリスクがあるため、当院では用いません。 - 麻酔の定期投与
・分娩後の処置が終わるまで、1時間おきに定期投与
・少しでも痛みがある場合は、
内診や麻酔範囲を確認してスタッフが追加投与
※ご自身で麻酔追加できるボタンはお渡ししません。 - 麻酔効果が不十分な場合
・効果の強い薬を安全な条件で少量併用
・カテーテルを早めに入れ替え - 陣痛が弱い場合
・陣痛促進剤を点滴から少量ずつ投与
※分娩が円滑に進み、麻酔薬の使用総量が少なく済みます。
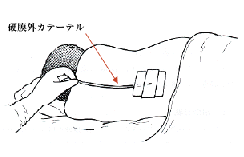
注意事項
- ※スタッフの管理体制
- 麻酔処置は、当院の麻酔科専門医もしくは麻酔科専門医が技術認定した産科医が行います。
- 麻酔薬の使い方は、院内でプロトコールを統一することで安全管理を徹底します。
- 安全の確認と技術向上のために、毎月すべての麻酔記録を振り返り、スタッフミーティングを行います。
- 危機対応シミュレーションを定期的に行います。
- ※麻酔中の出来事
- 硬膜外カテーテルを挿入すると、まれに一瞬の足のしびれを感じることがありますが、一過性であれば問題ありません。
- 麻酔が効き始めると、下肢に膜が張ったようなしびれ感が現れますが、下肢がある程度動いていれば問題なく、麻酔が終了すれば数時間で効果が消失します。
- 下肢の動き具合には個人差があり、歩行ができるくらいの方もいますが、少し重たくなる方もいますので、安全のために麻酔開始〜終了後数時間は全員ベッドの上で過ごしていただきます。
- 麻酔の定期投与が始まると、母児の状態が安定している方には、飲食(水、飴、ゼリー飲料)を提供します。
- 定期的に導尿をして、膀胱の負担を和らげます。
- 分娩が進行すると、児頭が肛門周囲を強く圧迫するので、不快に感じる時があります。
- 分娩の終盤は子宮収縮が強くなり、腹部の強い圧迫感も感じますから、それを目安にしながら、しっかりといきんで分娩の体勢をとります。
- 会陰部の切開や裂傷縫合を行う場合、通常は追加の麻酔が不要であり、生まれたての赤ちゃんの様子を落ち着いてご覧いただけます。
- 当院の麻酔方法が原因で出血が増えたり、胎児が仮死になることはありません。
- ※分娩後の流れ
- 分娩後の処置が終わればカテーテルを外し、内服の鎮痛薬に切り替えます。
- 分娩の約6時間後には歩行や排尿の練習を行います。
重要事項
当院が目指す麻酔管理
効きの良い硬膜外カテーテルを入れることにこだわっていますから、使用する局所麻酔薬は、0.09%というかなり薄いものだけ十分です。濃い薬で誤魔化すような管理は行いません。
痛みゼロを目指しながら、子宮収縮を止めず、運動神経の機能を維持します。お母様自身の力で主体的に、そして記憶に残る素敵なご出産ができるよう、心がけています。
緊急帝王切開への備え
麻酔薬自体が原因で帝王切開率が上がることは、ありません。 ただし、胎児心拍数の異常や胎盤早期剥離などによる出血など、通常分娩で起こりうるトラブルは、麻酔分娩の施行の如何に関わらず発生します。詳しくは「特別教室」、「もしもの帝王切開が愛しい絆に変わる教室」で一緒に学びましょう。
帝王切開の麻酔について無痛分娩(硬膜外麻酔分娩)ができない場合
当日に以下の状況になれば、できません。
- 麻酔処置が間に合わない(ご入院時点でまもなく分娩になる等)
- 母児の状態が不安定(緊急帝王切開等を検討)
- 止血・凝固検査の異常(硬膜外血腫のリスク)
- 皮膚の感染症(硬膜外膿瘍や髄膜炎のリスク)
- 技術的に困難(神経障害や頭痛のリスク)
他にも、事前に以下の状況などが分かれば、安全な周産期管理のために高次医療施設への紹介を行います。
- 気道確保が困難
- 入院時にBMI 30 以上が見込まれる
- 背骨の変形や神経疾患がある
- 心臓、脳、血液などに疾患がある
当院の成績と最新情報
数多ある無痛分娩施設の中から当院をご検討いただきありがとうございます。1997年から始まった当院の無痛分娩(硬膜外麻酔分娩)についての詳細は、下記にて情報発信しております。ぜひご覧ください。
⇒ 無痛分娩施設情報一覧 (PDF) ⇒ 無痛分娩(硬膜外麻酔分娩)看護手順 (PDF) Instagram アカウントご予約の流れ
- 教室受講(各自でご予約)
教室一覧必須 特別教室 または ふむふむなるほど麻酔教室(zoom) おすすめ ソフロロジー教室、母乳育児教室
もしもの帝王切開が愛しい絆に変わる教室(zoom)
マタニティビクス、コンディショニングヨガ
- 麻酔外来受診(後期検診でご案内)
- 入院時に麻酔同意書を提出
帝王切開の麻酔について
当院では、脊髄くも膜下麻酔+硬膜外麻酔で管理しています。
ご希望に応じて、麻酔科専門医が鎮静を行うことも可能ですので、ご相談ください。
なお、緊急手術等の場合は、安全性や緊急性を考慮して、麻酔処置内容が変更となる場合があります。
例)無痛分娩(硬膜外麻酔分娩)から緊急帝王切開に切り替わった
- 麻酔分娩用の硬膜外カテーテルの効果が信頼できる場合
→硬膜外麻酔を継続利用 - その他
→新規で麻酔追加:脊髄くも膜下麻酔+硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔
妊娠している限り、突然帝王切開に決まる可能性があります。どんな帝王切開でも、大切に、そして素敵な思い出にしていただけるよう、当院ではお母さま全員を対象に「もしもの帝王切開が愛しい絆に変わる教室」をオンラインで開催しています。麻酔科専門医と公認心理師がご案内します。ぜひ一緒に心の準備をしてみませんか。ご予約お待ちしております。
もしもの帝王切開が愛しい絆に変わる教室